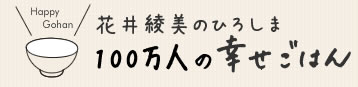先日テレビを観ていたら、芸術的サーカスで有名なシルク・ド・ソレイユの団員が
「定期的にビーツを食べてデトックスして肉体疲労を取る」と話していました。
トップアスリートの発言だけに説得力があります。
「ビーツ」とは、ロシアのボルシチでおなじみの野菜。
赤かぶのように見えますが、ホウレンソウと同じアカザ科で
甜菜(サトウダイコン)の仲間です。
調理すると手もまな板も真っ赤に染まる色素成分はベタシアニン、
強い抗酸化力があり、体内の細胞を活性化してくれます。
また、ビーツの成分として近年注目されているのが、
「NOエヌオー)と呼ばれる一酸化窒素です。
これは全身の血液の流れ良くし、、血管をしなやかにして拡張させ、
脳や心臓病の原因となる血栓を予防するといわれます。
さらには血液の量を増やして体内の酸素を効率良く使う手助けをするため、
筋肉を増強し、持久力と疲労回復力を高める働きをします。
まさに若々しくいた人、元気に動きたい人のための野菜ですね。
かなり硬い野菜なので、時間をかけて茹でるか、
生のまますりおろして使います。
今朝は、すりおりしたビーツに豆乳、オリーブオイル、ハチミツ、塩こしょうを合わせ、
ソースにして野菜と一緒に食べました。
これが世界三大スープのひとつ{ボルシチ」